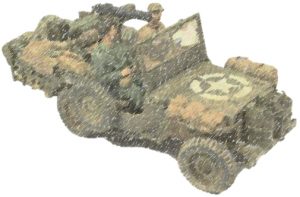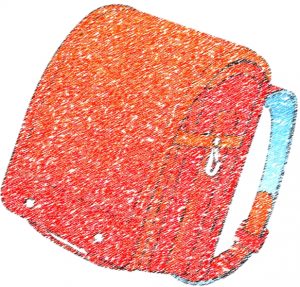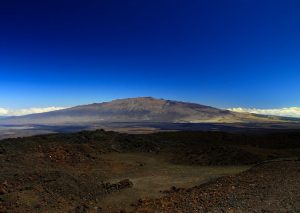私は、二人の祖父(お爺ちゃん)っ子。父親の顔を知らずに育ったけれど、幼い頃から小学・中学・高校までを父方母方のお爺ちゃん二人には、とても可愛がっていただいた。
この二人のお爺ちゃんとの思い出を振り返えっていたら、これは、私の看護における感性が芽生えていく過程の一つとして見過ごしてはいけない二人との暮らしじゃないのか? ハッと気づかされたままに、私の思い出の一頁として書き記すことにしました。
第一話 父方のお爺ちゃん。
彼は、お寺の和尚さん!禅宗の僧侶として住職をしておりました。面長で華奢な顔つきをしていて、若い時はきっとモテたにちがいない色香漂う寡黙なお人柄でした(写真で見る限り私の父は、お爺ちゃん似なのです)。
他人様の嫌事、悪口は耳にしたことなく、毎日の定番の仕草は、観音堂でのお経を唱えた後、特に秋から冬の間には、静かに火鉢の傍に座り、灰の中にくべられていたひとかけらの残り炭火を手繰り出し、それを囲うように炭を重ね置き、しばし火の熾るのを整えてから、一合のお酒を入れた鉄瓶をかけて、ゆっくり、しゅんしゅんと湧かし始めるのです。私は、何時からともなくそのそばに座って、鉄瓶を眺めたり、お爺ちゃんの仕草を見やったり、無言の空間で目を合わせたり…と、少々おませな座姿ではあったか?とは思うが、お爺ちゃんと私の二人きりのその時間は、苦痛でもなんでもなく、無言と静かな語らいの安らぎが流れていたことは、確かな記憶として残っている。
やっぱり、少々おませさんだったかもしれないが、良く笑う子でもありましたよ。
 村郷の山の中腹に建てられているお寺は、その構えからして由緒あるお寺の佇まいで、広い敷地には、大きな蓮池があり、蓮の花が咲き蓮の実が生れば、Y字型にした竹先で実を刈れば、お婆ちゃんがそれをこしらえて食卓に載せてくれていました。コリコリと美味しく、また粉にしては蓮餅にもしてくれて、美味しいとか不味いとかではなく、へえ~?!ってな珍しい食べ物感覚で頂いたかしらね。蓮池はもう既に跡形もなく埋められて50年は経っており、蓮の実の匂いとか蓮料理の味はもう忘れてしまっている。
村郷の山の中腹に建てられているお寺は、その構えからして由緒あるお寺の佇まいで、広い敷地には、大きな蓮池があり、蓮の花が咲き蓮の実が生れば、Y字型にした竹先で実を刈れば、お婆ちゃんがそれをこしらえて食卓に載せてくれていました。コリコリと美味しく、また粉にしては蓮餅にもしてくれて、美味しいとか不味いとかではなく、へえ~?!ってな珍しい食べ物感覚で頂いたかしらね。蓮池はもう既に跡形もなく埋められて50年は経っており、蓮の実の匂いとか蓮料理の味はもう忘れてしまっている。
また、本堂の裏側にある前栽には、枝の張った柿の木が5~6本あり、何時も秋には美味しい実を付けていました。お婆ちゃんが申すには、「この柿はそこら辺にある柿とは違う珍しい柿で、とても美味しいんやから…」と。代替わりをして間もなく、その珍しい柿は伐採され、一面ツツジの花咲く庭になりましたが、柿名も思い出すことのできなくなった今は、ちょっとした悔しみが残っているかな。
お寺の外回りには、竹藪に囲まれた池があり、これは流石に不気味な池と心得ていて、近寄り難かったものです。そこから続く小高い丘を登っていくと墓群があり、その頃は土葬されていたので人魂と言われる空中を浮遊する火の玉にしばしば出くわしたものです。恐怖感で全身が固まり、怖さのあまりその度にお爺ちゃんにしがみついていたけれど、泣くことはしませんでした。この火の玉について、今思えば、まことに納得する科学現象であったわけです。火の玉の正体とは、遺体からリンという科学物質が出て、それが雨水と反応して光るというのであるというわけです。
「くわばら!あれ~!くわばら」と、念仏を唱えながら、お爺ちゃんにしがみついていたのかどうか…不明だが、怖いながらも泣くこともせず…の私に、禅宗僧侶の作務衣を着たお爺ちゃんが申すには、「何も怖いことではないからのう。お人が死んで、少し彷徨って成仏して往くんやからのう」???やんわりと支えられて、その静かな暖かさに安堵していたのだろと思っている。
子ども時代には、人の死の苦しみは解らなかったけれども、死人との対面の恐怖は、ず~っと付きまとっていてトラウマ的な思いにも覆われていてたが、そうこうしながら、村人の死を弔うお爺ちゃんの姿を、遠目に静かに追いながら、そのあり様を心に留め置いてきたように思われます。死に行く人々、亡くなられた人々と共に暮らし、村の住人同士の親しみの中で、静かに丁寧に弔うお爺ちゃんには、凛とした眺め様があり近寄り難くあったように思われます。一つのイベントを終えて、お寺に帰り来れば、お疲れさん!お帰り!いつもと同じように声を届け迎えていたお婆ちゃんもいた光景が思い出されてきます。
母と私の住まいは、お寺のお爺ちゃんの住まう場所から、山を下り(登りて)バス停までは40分、バスに乗車してわが住まいの駅まで30分の道程ですが、小学校入学以降は、私一人で、月一回~二回は往復したものです。しかし私はバスに弱く、バスに酔う様は、顔面蒼白、嘔吐で全身グタッとなる。バスの到着地点までを、懸命にながらえながら、いざ!バスから降りると、山道を歩くうちに気分快復して笑顔でお寺に到着。
「お爺ちゃん、お婆ちゃん、範子で~す」とご挨拶すれば、「おうおう、よく来たよく来た!一人で偉いわ!」と迎えてくれる。「ご飯食べたか?」は定番に聞くことばだが、私はいつも「お弁当持ってるから大丈夫」と云う。母は、必ず私に弁当を持たせて送り出してくれたけれど、これは当時の母の気遣いであり、父の居なくなった両親に迷惑をかけれないと何時も持たせてくれたお弁当でした。草むらでお弁当を開いて一人で食べる私には、寂しいとか哀しいとか感じたことはなく、村の土・草の匂いの中で気持ちよく食したものですし、田舎では、蛇やカエルやバッタ、ナメクジやイモリ・ヤモリなどとの出会いがある。血の気の引くような出会いに驚き逃げ帰るなどもあったが、無事に過ごし得たことに感謝の思いは深く残っています。
お婆ちゃんは小学5年時に、お爺ちゃんは中学生の終わりの時に他界しましたが、お爺ちゃんとは、息を引き取る間際まで、私が付き添って静かにお別れをすることができました。誰もがお爺ちゃんとの時間をこのように共有できたわけではなく、月2回ごとに尋ねていた私とお爺ちゃんの終わり方であるわけです。
一人住まいのお爺ちゃん家の往復の楽しみは、「またねえ~!また来るよ~!元気でね~!」何度も振り返りながら、大きな声で連呼しながら、山を下りて帰っていくというこの繋がりが、かけがえのない鮮明な思い出となって生き続けているのです。
おセンチになったかもしれませんが、私は人の死の向かい合い方、受け入れ方をお爺ちゃんとの思い出の中に養われていたように思います。