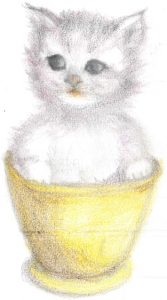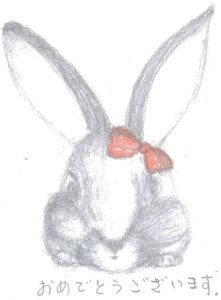2025年度には、人口の大きなボリュームゾーンを構成している『団塊の世代』は、75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護ニーズが、急速に増大します。
当然病床や人材を迅速・柔軟に確保できるよう、平時や感染拡大時の「状況に応じた対応方針を定めなければならない」というのは自明の事です。
地域における訪問看護の需要の増大に対応するには、訪問看護に従事する看護職員の確保が必要になり、在宅介護の需要の増大も伴なってくるわけです。
こうした状況の到来は、既に2000年初期に、2025年の人口動態に於いて
「超高齢社会、労働人口の減少」
が予測されており、危機感への認識が高まり、高齢社会の医療・介護体制の地域を包括する循環体制を整え、その充実化を進めていましたが、現実は、予想以上の速度で、超高齢社会・労働人口の減少・少子化(出生率の低下)が現実にやってきたわけです。
ある意味、この状況は予測されてしかるべきではあったはずで、既に現在、在宅系の看護師・介護職が不足している状況で、今後もさらに人材が必要とされるフィールドになっているのです。
殊に出生率の低下は、無策が招いた結果としての現状があると言っても過言ではないように思われます。
Indeed Japan株式会社は、25歳~49歳の正規雇用の転職経験者(現在就業中の正社員、会社経営者、会社役員、公務員、団体職員)の男女計8,399名を対象に、「未経験転職に関する調査」を実施し、現状の動向・問題点を発表されており、労働市場における人材不足を背景に、企業の未経験人材の求人や異業種・業界への転職が増加していることも示唆されています。
新たな仕事へのチャレンジやスキルの取得によって、キャリアの可能性を広げたいと考える人にとって有効な調査結果と思われ、未経験転職はひとつの選択肢となり得ていくのですね。
その様な社会の成り行き(変遷の動向)を積極的に認識するならば、異業種・業界への転職=(わが社のような)医療・看護・介護系の専門職へのチャレンジや、スキルの取得により、キャリアの可能性を広げてくることも大きく可能性は高いと希望を持つ次第です。
良き展望ではありますが、危機の中の展望の安定性は、やはり若年の労働者人口・高齢層の労働人口の増加を図ることに罹ってくるわけで、早期の突破口を創りだして対応していかなければならないのだと思います。
調査結果の要約をするならば、未経験転職の割合は、転職経験者の半数以上(54.3%)が未経験転職をしたことがある。
そのうち6割以上(61.3%)が「業種も職種も未経験」の転職をしたという事です。
未経験転職をした理由は、1位「給与を上げる」(25.8%)、2位「現状の業種・職種に不満」(22.5%)、3位「やりがい」(21.4%)や5位「新たな自分の可能性」「新しいことにチャレンジ」(ともに20.4%)という結果でした。
未経験転職の満足度においては、未経験転職をして「良かったと思う」人は61.4%、「悪かったと思う」人は全体で4.4%。
初めて未経験転職をした満足度は、年齢に関わらず高い傾向にあるといえます。
未経験転職を果たした人の「未経験転職」に対するイメージは、1位「新たな経験やスキルを積むことができる」(79.0%)、2位「新たな仕事やキャリアに挑戦できる⇒キャリアチェンジが実現できる」(77.4%)であり、35歳以上ではじめて未経験転職した人では「可能性の広がる転職である」が最多で8割以上(83.9%)という結果で、好感度が高いです。
未経験転職する人へのアドバイスとして、1位「年収や待遇などがどのくらい変わるのか確認しておく」(35.1%)、2位「自分のキャリアを振り返り、未経験でも活かせる強みを明確にしておく」(26.9%)、3位「無計画ではなく、先のキャリアを見越して未経験転職をしておく」(26.5%)という適切なアドバイスが発表されており、興味を持った次第です。
この事より学ぶべき見解は、人材紹介会社として転職希望者が、キャリアチェンジを望んでいなくても、面接時の特性から、気づいていないキャリアチェンジの特性情報を提供することが、大事な社会の活性化を図る一手ではないかと思われ、元気の出る社会情報であり、お互いの支え合いの情報提供が大事になって来ると思います。
このブログをお読み下さった皆さんが、何らかの形で刺激を受け、未来の自己像に思いを馳せる時、アイディアを浮かばせてみて下さい。
他人事ではない社会問題として、ご意見などフィードバックしてみるのもまた、楽しいことではないでしょうか?