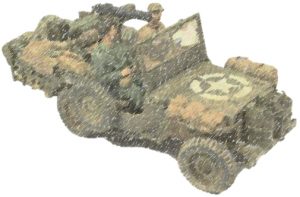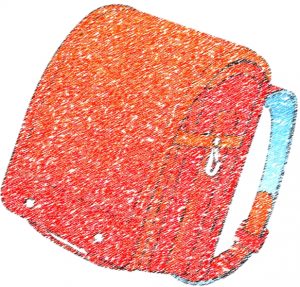18歳の娘が、南紀の町から大阪の都会に移り来て、看護学生寮(当時は看護短大以外はほとんど全て、寮生活が教育の一環として組み込まれていた)の一室にわが身を置いてしみじみと眺めてみた。土佐堀川に面して建っている横に長細いビルは、1階2階が看護学校、3階4階が学生寮となっており、寮は和室仕立ての4人部屋で、清潔感がありこじんまりと整っている。各人に、洋服ダンス風ロッカー、座り机、ベッドが、効率良くセッティングされていて、5年前に建てられたものだ。トイレ、洗面所と簡単な炊事場は共同で、此処も清潔に整えられていて気持ち良い。3学年60人の共同使用に手狭感、不備感なく、これからの3年間の学生生活の環境が整えられているのを感じ、気持ち新たに出発することになりました。
これからの3年間、待ち受けている試練は、「花も嵐も」。全く想像・想定するすべもなく、むしろ甘い期待に胸弾んでいました。
初めての寮生活。女子ばかりの看護学生生活。友としての密着度は、今まで経験したことの無い密室・密接至極。半年間は新人2名+上級生2名の4名構成で、その間、先輩から生活の基本や礼節に関する私達への伝授は厳しく、教務の先生方はじめ、まもなく出会うことが多くなるであろう病院職員の方々、学生間の先輩・後輩のわきまえなど、基本的で秩序ある関係性について伝授されました。
当時は新鮮な感覚で、熱心に聴いていましたが、生活が慣れて看護学生・寮生活への馴染が増すにつれ、自立性が確立してくる頃、今度はこの新世界の窮屈さに多少の不満を持ち始めましたが、やがて半年が過ぎて、同級生同士4人の同室になってからは、夜になると皆で学生生活論を交し溜飲を下げては、逸脱することのなきよう平静さを取り戻し、明日への再生に思い至らせ、平穏な眠りについていたものです。
看護学生としての寮生活はこのようにして、大きな問題もなく1年が過ぎ~2年目を迎え新入生を歓迎し、1年先輩・2年先輩となって3年間を過ごしたわけです。
後々になって、看護婦として社会人を歩み出してからは気づいたことですが、看護学生時代の先輩から伝授される社会生活の基本、同級生同士が培う人間関係力、3学年共々の一体感を共有し、人其々の多様性を認知し受け入れる許容性、生命力の礎になっていたのだと気づき、「同じ釜の飯を食って育つ」という経験は、無駄なプロセスではなかったと、悟りを得ました。
私は入学以来、生活の変化が大き過ぎたのであろうか、5月頃から体調に変化が及びはじめ、54~56㎏あった体重が7月には50㎏、女性の生理上の影響も出始め、月の徴は不定さが続くようになっていた。顔色は青白くなり、身体は痩せ、顔の生気が無くなる状態は12月頃まで続き48㎏に。その間、8月の夏休み帰省時には、教務主任の先生から「夏休み中、親御さんとこれからの進退について話し合ってきなさい」との厳しい指導がありました。これには、かなり反発を覚え、帰省しても母に伝えることなく学校に戻ってきましたが、教務主任には、学業を続行していく旨を伝え、決して快くは無い了解を頂き、「退学のすすめ」の受難をクリアしました。ですが、実は当時の私は、随分体調が不安定で、不慣れな学生生活のストレスによるものと自覚していました。
看護婦を目指して進学したのは私自身以外の何者でもなく、後ろ向きになりそうな自分に対して、誰も助けてくれる人はいない。母の長き闘病の苦しみに何も応えられなかった私の無力さが、看護婦への道を歩ませたのだから、これは頑張るしかない。その思いだけで、心のざわつきを抑制していたかな?
男女共学の小・中・高の学校生活から、女子ばかりの寮生活への変化は、相当なストレスでした。何しろ教科書は、医学書・看護学書に準じた基礎看護学諸々であり、私の考え及ばぬ世界に迷い込んだようで、学びの面白さを知るどころか、学び方が解らなかった。どのように気力を持ちあげて学んでいけば良いのか…?!と。
今でこそ「カルチャーショック」という言葉は、普通に取りざたされていますが、考えてみれば、当時の私は、異文化に接した時に受ける精神的な衝撃を受けたわけです。今まで習得してきた知識と現実の習得する情報の乖離が、まさしく大きくありましたし、新しき友達は、戸惑うことなく授業を受け、寮に帰っては復習を難なくこなしているように見受けられ、気後れする自分をひた隠して陽気を繕っていた私でした。
 ですから、勉強は寮で皆と共にではなく、学校の図書室で調べるでもなく、ひたすら、古めかしくも重みあるレンガ調の中之島中央図書館に通い、本の開き方、本の選び方等に関して、小さな声で図書館の方に教えて頂きながら、我が教科書の部分を捉えて、ノートに記述することを繰り返しながら、如何にも勉強した気分になって寮に帰ってくるという繰り返しを続け、果てしなき無駄骨を折っていた姿が、涙ぐましく哀れに思い出されてきます。
ですから、勉強は寮で皆と共にではなく、学校の図書室で調べるでもなく、ひたすら、古めかしくも重みあるレンガ調の中之島中央図書館に通い、本の開き方、本の選び方等に関して、小さな声で図書館の方に教えて頂きながら、我が教科書の部分を捉えて、ノートに記述することを繰り返しながら、如何にも勉強した気分になって寮に帰ってくるという繰り返しを続け、果てしなき無駄骨を折っていた姿が、涙ぐましく哀れに思い出されてきます。
しかし、この事態は、私の学生生活3年間を継続する底支えになっていたと思うのです。
馬鹿らしい遠回りの学習の仕方ではありましたが、やがて「今、何を教わり何が解らないのか?」同期生皆との交流の仕方が定まるようになってきて、2年生の夏休み以降は、私なりの歩み方が気負いなく是正され始めてきました。
当時の看護学生の教育カリキュラムは、実習時間が大幅に多く、私達は「学生とは名ばかり。半学生・半労働者じゃないの!」文句の極みを正義感で持って、諤々述べ合っていました。教務の先生方に説明を求めたりもしましたが、今思えば、教務の先生方は、学生に言われるまでもなく、基礎看護教育上の問題点を痛く自覚しながら、私達を教育されていたのですが…。
学生ってのは、ホントに青臭く、無垢つけき若者。若きエネルギーを、どちらの方向に飛ばし向かおうとさせるのやら…。多くの主張を正義と心得、簡単に譲ることはしない。良きにつけ悪しきにつけ、在り方によっては厄介で軌道修正の余地がないほどに頑張る。私もまた、そんな時代の中にあって、やはり看護学生生活(看護学校、寮生活の窮屈さと自由さの中で)は、青春の足跡として記憶に残っています。