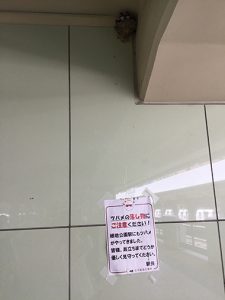年の瀬になりますと、やはりなんだかんだの大騒ぎとなるのは、忘年会かな?
年の瀬と云いますと「年末用語」として定着しているけれど、かつては、江戸時代に遡る江戸庶民の年末時に取り立てられる「ツケの支払い」に奔走する命がけの慌ただしい様に発しているようだ。
付け加えて、その語源をネットから引用すると、「年の瀬」は「川の瀬」を表しており、「川の水位が低く浅い部分」を指し、川の流れが勢いを増し、急激に早くなるスポットのことで、川の瀬を渡るには、船ですら困難で、ましてや歩いて渡るとなると「命がけ」となる。「年の瀬」は、このような必死で危機迫るという意味合いの言葉で、その語源は「ツケの支払い」ということになる。
現代に於いては、「必死の支払い」どころか現実感のない(重みの無い)カード払い。
東京オリンピック・大阪万博を前に、既にカード支払いが当たり前の世界からの来訪者が押し寄せてくれば、カード支払が瞬く間に浸透するだろうし、これまでと違う世情風景になるのだろう(ちょっと、どんな世の中になっていくのか、想像難しで解らないワ!!)
今はもう、年の瀬風景というわけにはいかないが、昔はやはり年末・年の暮は、「餅つき」風景がありましたよね。一軒に必ずというか、町内「組」毎に、餅つき用具が備えられていて、杵・臼(御影石・けや木)・臼台(石・木)その他の小道具(もち米炊窯、かまど、餅蓋、他いろいろ)が出そろい、家人や町内(組)会人などが、忙しく働きまわり、大きな掛け声や、杵を振り落す音などが、響き渡ったものです。
コメ離れ現象が起きて、正月には餅を食べる家族も少なくなってきている昨今ではあり、話題にすれば、ちょっとヤバくてダサい話になってくるわね。
しかしながら、私は「おもち」が好き。年がら年中、それなりに、おもちを食べる機会が多くあるかな?(私に届くお餅は、みな福餅なのよ。幸せ餅よ)
 今朝(12月21日)もTV朝日で紹介されていたのだけれど、和歌山県は半島の南北津々浦々、結構な市町村で、餅まきがあるの。神社仏閣が多いせいだと紹介されていたが、家を新築するとき、神社での祭事・イベントがあるとき、等々、とにかく何かにつけて餅まきがある。
今朝(12月21日)もTV朝日で紹介されていたのだけれど、和歌山県は半島の南北津々浦々、結構な市町村で、餅まきがあるの。神社仏閣が多いせいだと紹介されていたが、家を新築するとき、神社での祭事・イベントがあるとき、等々、とにかく何かにつけて餅まきがある。
私は長く和歌山を離れて大阪に居住しているのだけれど、郷里の親族から、いまだに 餅まきがあったからと、ゲットした(ビニール袋に入った)紅白の餅を送ってくれるのです。とにかく餅好きの私。ありがたく頂き、雑煮・焼き餅・ぜんざい・きな粉餅などにこしらえて食べているのである(餅は全然飽きないねえ!)。
さて、今年もいよいよあと一週間。平成30年を生きて、皆様にとっては如何なる平成30年でしたか?2019年からの元号は、まもなく発表されるでしょうが、どんな意味合いをもって、国民に届けられるのでしょうか?
それ程に深い極みを持って情熱をもって、世情・世界を語り論じ合うことの少なくなった平成30年は穏やかではあったけれど、平和的ではあったかな?そう思うけれど、そうではないんじゃない?平成の終わりに、私の平成時代の趨向いまだ定まらずでございますよ。
新年2019年は、新しい元号の始まり。なのですから、いろいろ考えるきっかけにしてみても良いですよね(考えてみるべきですよね)。
この一年間(かれこれ数年になりますが)、稚拙なブログに目を通していただきましてありがとうございました。
ではでは皆様、新しき年に向けて、希望の年でありますよう、そのように祈りつつ、今年に感謝して、平成に幕を下ろしましょうか。
皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。