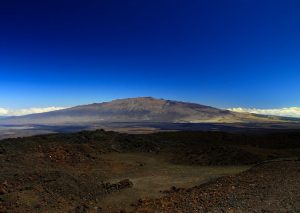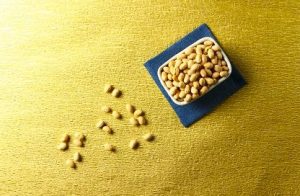昨年の5月「令和」になって、初めてのお正月を迎え、色々と空気の一新がそこかしこにあっているようにも思え、希望的に受けとめうる清々しさを覚えました。
が、しかし中国での新型肺炎のニュースが飛び込んできました。当初の構えは三段の構えさながら呑気に間抜けて眺めていましたが、日ごとにこのニュースは、気をつけなきゃいけないよ!のトーンに。そして一挙に中国の主要都市部に置いても蔓延し、人から人への感染である旨の注意喚起が現時点で出されています。
やはり、単なる風邪と侮らず、慎重に感染制御を意識して日常動作、体調変化に気を付けていきましょう。
私は、昨年暮れより正月3日間、息子夫婦と孫(男児)一人を我が家に向え、賑やかな笑いの中に、久しぶりで身を置くことができ、家族が集う幸せ感を味わいつつ過ごすことができました。日ごろは、単体で私一人の生活体ですから、何分にも平素よりは、立ち仕事・あれこれ忙しさのいる力仕事の動作が多く、身体中痛みを積み込んでいくような感覚の中で、孫のため、息子夫婦のためと、そのように立ち振るまっている自身の健気さに喜び、感謝を想うお正月の日々でした。
体力の減退を感じざるを得ない今日この頃故、老年の呼吸器系感染は軽視しないで、気を付けたいと思っています。
2020年は始まり、皆様は、年の初めの希望をどのように定め、歩み出されたことでしょうか?令和2年の話題性は、何といっても オリンピック・パラリンピック。すぐそこに迎えようとしているのですから、前哨戦の盛り上がりたるや全国規模に取り組んでおりますよね。夢・希望を膨らませた聖火ランナーの方々、各オリンピック種目別の代表選手の決定戦と選手決定等々、観戦チケットの売れ行きも、多少トラブルを引き起こしながら好調に走っているようです。TVチャンネルは、何処を回しても、オリンピックイヤー モード。いやはや恐れ入ります。私は、普通にTVを通してオリ・パラ感染(観戦)させていただこうと思います。
一方、政治的には、緩みがポロポロ、次から次へと横柄な国会議員の逸脱した特権志向にうんざりしていますが、やはり何よりも経済が強い(と言っても良いかな?)日本(世界)の経済の行方が、私たちの生活レベルを上下左右にかじ取りをしてくれていますが、何せ、私たちは今や、しっかり働かなければ…生活への影響は大きい。
今の日本で幸せな働き方はどのようにしてできるか。働き方改革という言葉が、ここ2~3年ほど前から、人生訓のような問いかけで云々されているが、具体的な対策(確かさ)は、まだそう簡単に表出されているわけではない。むしろ、じくじくと女々しい呟きが吐露されて前向きになるのが遅々とならざるを得ないのかしら?
急激に進む少子高齢化に処しきれぬ波の勢いというか掴みどころのない波の弾というか、社会的発展も自己の人生設計も、楽しみある確たる将来への構築が描けない。考えにくく、的を得にくく、生きづらい思いになって呻いてしまいそう。
政治家が「働き方改革」の方針を打ち出したとて、それがどのような方向性で整備されようとしているかと言えば、なかなか中途半端で、満足感が盛り上がってこない?ように思うが…。男性の育児参加も、どんな思想哲学(ちょっと偉そうに言ってしまいますが)、生活様式の現状に沿って打ち出されているのか…。小泉環境相の育児休暇宣言は、安っぽく感じられ萎えてしまいませんか?
「働き方改革で時短になってもノルマがきつくなるだけ。自分としての利益=給与から得られる満足感-労働を維持するための資産となる有益な費用」とも考えれば、大きく惑わされることなく、自己の人生の資産力(スキル力)を熟成しえる仕事が重要と捉えることができれば、楽になるだろうか?そんな心配をやはり吐露したくなるわ。
世の中、進みゆく方向性の質に対して、私達が自覚を成し得ないままに流れに任せていけば、その空気の怖さは倍返しで反ってくるように思い、これって、不気味だなあ!
でも、あっちこっちで、小さな試み、知恵を具現化して、健気な活動をしているニュースも見聞きしますよね。メディアの方々に頑張っていただいて、大いに発信していただけることも期待できるのだわ。
私は、何が言いたいのかな?
70歳を過ぎても働こうよ。今の高齢者世代は、逞しく強いんだよね~!!老いも若きも、共に「働き方改革」に向って知恵を出して、楽しく健康的に、私たちの資産力を熟成しうる働き方を創り上げていきましょうよ。って言いたいわけよ!嘆いちゃダメ!前を向いて生きよう!
では、この一年、皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。